皆さんは仕事を辞めることになった際、その後の生活について考えたことはありますか?
会社から突然雇用を切られてしまったり、仕事を辞めざるを得なくなったりするケースがあるかと思います。
今まで勤めてきた仕事を辞めた後、1か月以上再就職先がない方向けに、いくつか紹介していきたいと思っています。参考になればありがたいです。
仕事を辞める前にやっておきたいこと
仕事探しのほか、長期にわたって仕事に就けない状況が続くこともあるので、それらも踏まえて参考にしていただけると幸いです。
社会保険や雇用保険に加入している場合と、未加入の場合があるかと思いますが、それぞれに分けて紹介します。
最低3ヶ月程度の生活費を確保しておく
退職が1か月以上先で、生活費に余裕があれば、3ヶ月分の収入を貯蓄して確保しておくことおすすめします。
私の場合は時間に余裕がありましたが、お金を確保する余裕がなかったので、本業の有給休暇を消化しながら、フルタイムで副業をして貯蓄を確保したことがあります(副業ができない場合はあまりおすすめしません)
また、仕事を辞めてからのアルバイトやパート、派遣、スキマバイトなども検討してみましょう。
源泉徴収票の発行
源泉徴収票は、その年に稼いだ金額と納めた所得税、社会保険料などの計算を行った収入の証明になる書類です。通常は年末調整を行った後で発行されますが、前職で最後の給料が支払われるタイミングで発行の依頼をしてみましょう。
再就職した時期にもよりますが、再就職していれば年末調整、確定申告で必要になるため、前職の源泉徴収票があれば、再就職先で合算、確定申告で申告しましょう。
マイナポータルの連携、離職票または雇用保険被保険者証の発行依頼
社会保険や雇用保険に加入している方で、退職時に再就職先が決まっていなければ、離職票の発行を依頼することをおすすめします。離職票はハローワークにて、失業給付の申請で必要になります。
会社や時期によって離職票の発行が大幅に遅れる場合がありますが、発行に時間を要する場合は、雇用保険被保険者証を発行してもらいましょう。特に3~4月ごろは発行が遅い傾向があるようで、退職日から12日経過した日までに離職票があれば、失業給付の申請を行うことができますが、仮に間に合わなかったとしても、雇用保険被保険者証でも仮申請が可能です。離職票が届き次第、ハローワークに提出しましょう。
2025年1月20日より、マイナポータルにて離職票が受け取れるようになりました。マイナンバーカードをお持ちの方は、離職前にマイナポータルと雇用保険Webサービスの連携を行うことで、前職から離職票を取り寄せる手間が省け、ご自宅で印刷、PDFで保存が保存できます。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
健康保険資格喪失(脱退)証明書の発行依頼
社会保険に加入している方が離職すると、健康保険組合の脱退が必要になります。健康保険資格喪失証明書を発行してもらい、再就職先や新たな健康保険組合、国民健康保険の窓口に提出しましょう。
また、離職先の健康保険証は退職日の翌日以降は使用できないので、医療機関に受診しなければ、速やかに返却しましょう。
自己都合退職なのか会社都合退職なのか証拠集めをしておく
離職票には、事業主(会社)が記載した離職理由と離職者が記入する離職理由の欄があります。ハローワークに行った際、担当者から離職した理由を聞かれます。
それをもとに会社都合退職なのか自己都合退職なのかを判断し、失業給付を申請する手続きを行います。会社都合退職なのか自己都合退職なのかで失業給付に大きな差が発生します。
ただし、2025年4月に雇用保険法が改正され、2025年4月1日以降の退職日の方は、給付制限は2か月から1か月に短縮します。
詳細は以下のリンクを参照してください。
また、よくあるトラブルとして…
- 会社との雇用契約が切れたにも関わらず「会社都合退職」ではなく「理由のない自己都合退職」
- 病気を理由に退職したものの「理由のある自己都合退職」ではなく「理由のない自己都合退職」
などにされていたことなどが挙げられます。
その際は、ハローワークで異議申し立てを行うか、就労可否証明書の提出が必要になります。いずれにせよ、離職後にひと悶着あるのは嫌かもしれませんが、先駆者のブログも参照していただけると、離職前にどう行動するべきかは見えてくるかと思います。


仕事を辞めた後にやっておきたいこと
仕事を辞めた後は比較的に時間に余裕が出てくるかと思います。ただ、ハローワークやお住いの自治体窓口などの手続きが発生します。
さらに、仕事をしないと無収入になるため、貯蓄や収入確保の対策が必要になります。
そのような点も踏まえて紹介していきます。
アルバイトやパート、派遣やスキマバイトを探す
無職状態になると収入がないため、比較的に時間に余裕のあるバイトを探して、仕事をすることをおすすめします。ただ、貯蓄があったり、病気が原因で働けないといったことで、絶対ということではありません。
この後紹介する「失業給付の手続き」を行うと、待期期間中は働くことができず、失業給付を受けている期間は、目安として週20時間以上は働くことはできません(雇用保険の加入対象に該当するため)。
仕事を探しながら働くことはできますが、働いたり、お手伝い等をしたりして収入があった際は、失業認定申告書に申告する必要があります。
国民健康保険に加入する・国民年金に加入する
扶養に入らず、健康保険任意継続制度に加入しなければ、お住いの自治体の国民健康保険の加入をおすすめします。
同時に国民年金の加入手続きも行っておくと良いでしょう。年金事務所でも自治体窓口でも対応してくれます。退職してから14日以内には手続きを行ってください。
また、ハローワークで離職票を提出し、雇用保険受給資格者証が発行された際、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、国民健康保険の保険料の減免が受けられます。
扶養に入る・健康保険任意継続制度に加入する
お住いの自治体の国民健康保険の加入しなければ、世帯主の扶養に入るか、離職先の健康保険任意継続制度に加入しましょう。扶養に入れば、保険料は被保険者が納めるので、金額を支払うことはありません。
任意継続制度に加入するか国民健康保険の加入かで保険料が大きく変わってくるので、以下のサイトで比較して、いずれかに加入しましょう。その際は、資格喪失証明書が必要になります。
いずれにせよ、健康保険に加入しないと医療機関で、自己負担が大きくなってしまうので、加入することを強くおすすめします。
ハローワークに行き、失業給付の手続きを行う
働く意思はあり、なかなか内定がもらえず、転職活動中であれば、ハローワークに行って失業給付の手続きを行いましょう。
退職日翌日から10日以内に前職の勤務先から離職票が届いたり、マイナポータルで発行されたら、お住いの管轄のハローワークに行き、離職票を提出しましょう。この際に離職票の内容を読んでおくと、窓口でスムーズにいったり、離職理由の相違を見つけることができます。
会社や時期によって離職票の発行が大幅に遅れる場合があります。すでに会社側から発行に時間を要する場合は、雇用保険被保険者証を発行してもらい、ハローワークに行って仮申請を行いましょう。
退職日翌日から12日以降、離職票が届かなかったとしても、雇用保険被保険者証でも仮申請が可能です。離職票が届き次第、ハローワークに提出しましょう。
失業給付の手続きを行った日(受給資格決定日)の翌日から7日間は待期期間、就職活動は行えますが、失業状態を確認するため、アルバイトや派遣など、働くことができません。
待期期間終了後は週20時間を超えない範囲で働けますが、失業認定申告書で申告します。虚偽の申告をすると、法律で罰せられるため、しっかりと申告しましょう。
求職活動の実績と認定日等で定期的にハローワークに通う
失業給付の手続きを行った日(受給資格決定日)と職業相談、セミナー、説明会、失業認定日でハローワークに定期的に通います。月に最低2回以上、実績を作る必要があります。通っていれば、ハローワークで、雇用保険受給資格者証は担当者が記載、失業認定申告書に実績を記入できます。
認定日は固定のため、必ずその日に行く必要があります。認定日当日に職業相談があれば、次回提出する申告書に記入して提出することができます。就職が決まるまで、または自営業等を始めるまでは、求職活動の実績を作り、失業給付を受給できます。
番外編 教育訓練給付制度や職業訓練
ハローワークでは、失業給付や職業相談のほか、セミナー以外にも、教育訓練給付制度や職業訓練を利用することができます。
教育訓練給付制度や職業訓練制度を利用する
雇用保険に加入していた期間に応じて、教育訓練給付制度を使って国家資格を取得したり、職業訓練校等に通学しながら、技術習得に向けての訓練を受講したりすることもできます。
今現在、リスキリング(学びなおし)を推奨しており、新たな転職で再就職で賃金アップやキャリア形成を図っているので、転職する際の資格取得の一つとして考えてみましょう。

まとめ
いかがだったでしょうか。仕事を辞める前と辞めた後で、それぞれやることが見えてきたと思います。
必要な書類や手続きが多くあるので、求職活動をしながら仕事をする合間に手続きを行うのは大変かと思います。
無事に就職が決まり、ある一定の基準を満たせば、再就職手当が支給されます。仕事を辞めてしまったり、失ってしまったりしても、諦めずに再就職や独立などを視野に考えて行動していってみてください。
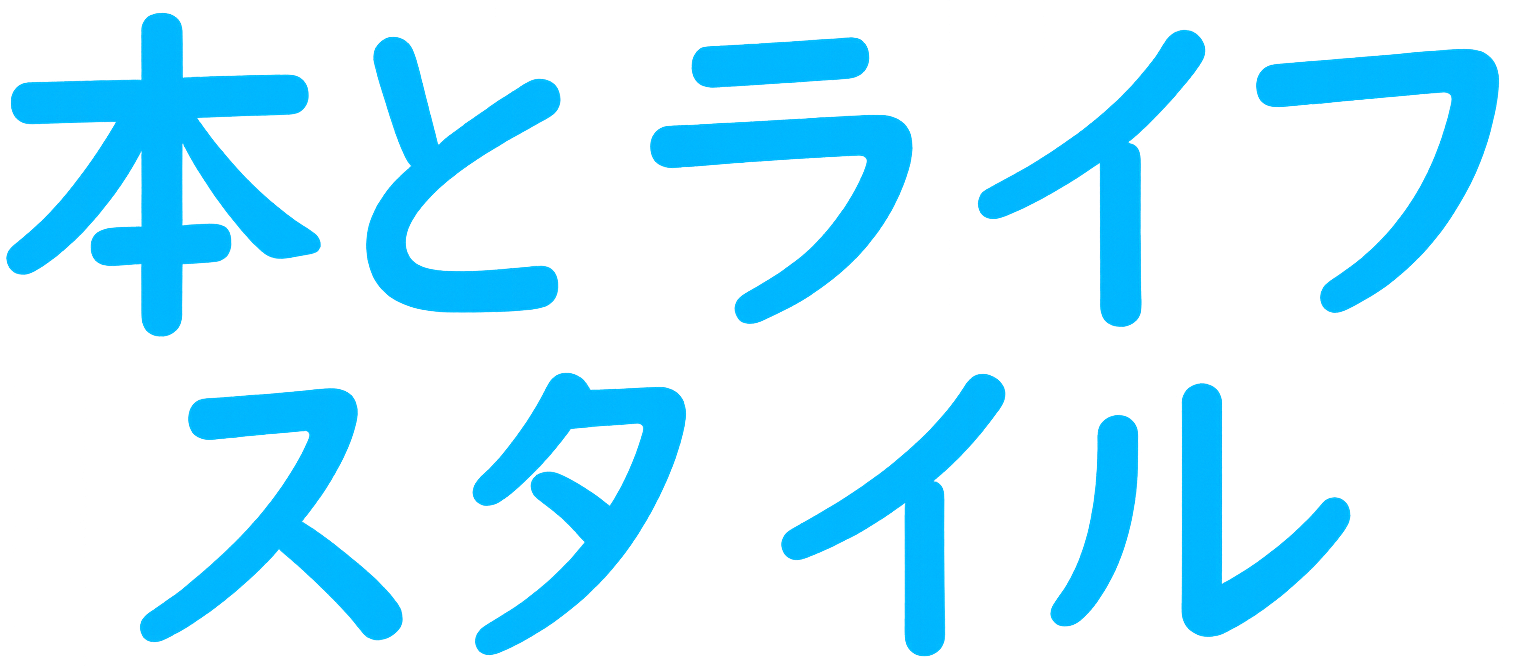

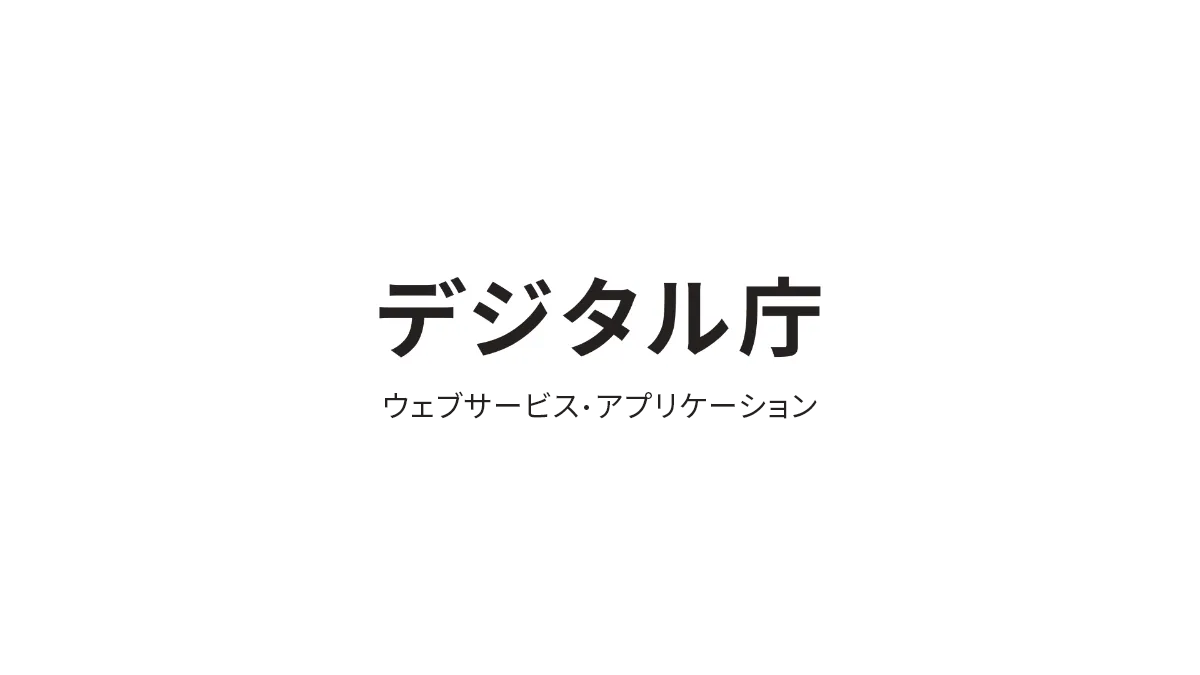



コメント